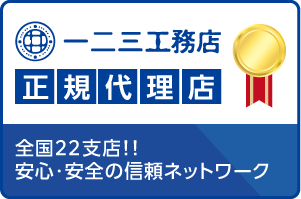冬は日が当たらない室内は冷えやすく、場合によっては外よりも寒いと感じる場合もあるでしょう。寒さを放置しておくと健康にもよくありません。
本記事では、寒い家を温かくする方法として自分でできる対策と断熱リフォームの両方を紹介します。家の中が寒いので何とかしたいと考えている方は、参考にしてください。
断熱材がない家の寒さの原因を徹底解説

断熱材がない家は、冷気が侵入しやすく、暖気が逃げやすい構造になっています。そのため、冬場は特に室温が下がりやすく、寒さを感じやすいのが特徴です。では、具体的にどのような原因で寒さを感じてしまうのでしょうか?以下、断熱材がない家の寒さの原因を4つの側面から詳しく見ていきましょう。
気密性の低さによる隙間風
断熱材がない古い家屋は、気密性が低い場合が多く、窓枠や壁の隙間から冷風が吹き込んでくる「隙間風」が発生しやすいです。この隙間風は、体感温度を著しく低下させ、室温を下げる大きな原因となります。特に、風の強い日や、建物の構造上の弱点となる部分では、隙間風による寒さが顕著に現れます。
窓からの熱損失
窓は、家の中でも特に熱が逃げやすい部分です。断熱材がない場合、窓ガラスから室内の暖気が外に逃げていく熱損失が大きくなり、室温の低下につながります。特に、古いタイプの窓ガラスは、断熱性能が低いため、この問題が深刻化します。窓からの冷気は、直接肌に当たるため、体感温度を大きく下げる要因となります。
床からの冷え込み
床下からの冷え込みも、断熱材がない家では大きな問題となります。特に、コンクリートの床の場合、地面からの冷気が直接伝わってきます。この冷気は、足元から冷える原因となり、身体全体の体温低下を招きます。床材の種類や床下の状況によっては、この冷え込みがより顕著になります。
壁からの熱伝導
外壁からの熱伝導も、室温低下に大きく影響します。断熱材がない場合、外気温が低い冬は、外壁を通じて室内の熱がどんどん外に逃げていきます。この熱伝導は、壁の素材や厚さ、外気温によって大きく変化します。特に、薄い壁や、熱伝導率の高い素材を使用している場合は、熱損失が大きくなります。
これらの原因が複合的に作用することで、断熱材のない家は、想像以上に寒く、不快な空間になりがちです。次の章では、これらの問題を解決するための具体的な対策を解説していきます。
寒い家を放置する弊害

寒い家で暮らしていると生活の質が下がるのはもちろんのこと、健康被害が起こる可能性があります。一例を挙げると、ヒートショックです。ヒートショックは温度差がある所へ短時間で移動すると、血圧が急激に上下して心筋梗塞や脳出血、脳梗塞などの引き金になる症状です。高血圧の高齢者が特に危険です。
ヒートショックは温かい部屋から温度の低い脱衣所、温度が高い浴室に移動する際になりがちなイメージがあります。しかし、家の中で温度差が大きいと、部屋の中から外へ何度も移動しただけでヒートショックの危険性が高まります。特に、高齢者が1人暮らしの場合、倒れても長時間気づかれにくいといった恐れもあるでしょう。
窓・ドアの防寒対策:隙間風を防ぎ、熱を逃さない
断熱材がない家は、窓やドアからの隙間風によって室内の暖気がどんどん逃げてしまいます。この問題を解決し、快適な室温を保つためには、効果的な防寒対策が不可欠です。ここでは、手軽にできるものから本格的なリフォームまで、様々な対策方法をご紹介します。
隙間テープやパッキンによる気密性の向上
最も手軽で費用対効果の高い対策として、窓枠やドア枠の隙間を埋める方法があります。ホームセンターなどで手軽に購入できる隙間テープやパッキンは、様々なサイズや素材が揃っており、窓やドアの種類に合わせて選ぶことができます。 これらのアイテムを隙間部分に貼るだけで、驚くほど隙間風が減り、冷気の侵入を防ぐ効果が期待できます。 作業も簡単なので、DIY初心者でも安心して取り組めます。
断熱カーテン・ブラインドの活用
断熱効果の高いカーテンやブラインドは、窓からの熱損失を大幅に削減します。一般的なカーテンよりも断熱性に優れた素材を使用したものや、空気層を作り出すことで断熱性を高めた製品など、様々な種類があります。 特に、厚手の生地や遮光性が高いカーテンは、冷気の侵入を防ぐだけでなく、室内の保温にも効果を発揮します。 デザインも豊富なので、お部屋の雰囲気に合わせて選ぶことができます。
内窓の設置による断熱強化
より本格的な対策として、内窓の設置が挙げられます。既存の窓の内側に新たな窓枠とガラスを設置することで、空気層を作り、断熱性を大幅に向上させます。 内窓は、二重窓とも呼ばれ、高い断熱効果と防音効果も期待できます。 初期費用はかかりますが、長期的には光熱費の削減につながり、費用対効果も高いと言えるでしょう。専門業者に依頼する必要がありますが、快適な室内環境を実現したい方にはおすすめです。
窓ガラスフィルムの活用
窓ガラスに貼るだけで簡単に断熱効果を高められる窓ガラスフィルムも有効です。 様々な種類があり、断熱効果だけでなく、UVカットや飛散防止効果のあるものもあります。 施工も比較的簡単で、DIYでも行えます。 費用を抑えつつ、手軽に断熱性を向上させたい方におすすめです。ただし、フィルムの種類によっては、窓の外観に影響を与える可能性があるため、事前に確認が必要です。
これらの対策を組み合わせることで、窓やドアからの冷気侵入を効果的に防ぎ、より快適な冬を過ごすことができます。 ご自身の状況や予算に合わせて、最適な対策を選び、寒さ知らずの冬を迎えましょう。
床の防寒対策:足元から暖かく

床からの冷え込みは、体感温度を大きく下げる原因の一つです。特に断熱材のない家は、床からの冷気がダイレクトに伝わってくるため、足元が冷えてしまうと全身が寒く感じてしまいます。そこで、この章では足元から暖かく過ごすための効果的な対策をいくつかご紹介します。
断熱マットやカーペットの敷設
最も手軽で費用対効果の高い方法が、断熱マットやカーペットの敷設です。様々な種類、厚さ、素材のものが市販されており、お部屋の雰囲気や好みに合わせて選ぶことができます。厚手のものは断熱効果が高く、ふわふわとした肌触りで快適に過ごせます。さらに、滑り止め付きのものを選ぶことで、安全面も確保できます。 選び方のポイントは、断熱性だけでなく、耐久性やお手入れのしやすさなども考慮することです。 例えば、ペットを飼っている家庭では、ペットの爪に強い素材を選ぶことが重要になります。
床暖房の導入
より本格的な対策としては、床暖房の導入が挙げられます。電気式や温水式など様々な種類があり、初期費用は高額ですが、一度設置してしまえば、長期間にわたって快適な暖かさをもたらしてくれます。 足元からじんわりと温まるため、部屋全体を暖めるよりも少ないエネルギーで快適な温度を保つことができます。ただし、導入には工事が必要となるため、費用や工事期間などを事前にしっかりと確認することが大切です。既存の床材の種類によっては、対応できない場合もありますので、専門業者に相談することをお勧めします。
ホットカーペットの使用
手軽に足元を暖めたい場合は、ホットカーペットが便利です。電気代はかかりますが、必要な場所だけをピンポイントで暖めることができるため、効率的な暖房手段となります。 様々なサイズや機能が用意されているので、お部屋の広さや用途に合わせて選ぶことができます。タイマー機能付きのものを選べば、無駄な電力消費を抑えることも可能です。ただし、長時間使用すると電気代が高くなる可能性があるため、こまめな温度調整やタイマーの使用を心がけましょう。また、小さなお子さんやペットがいる家庭では、安全面に配慮した製品を選ぶことが重要です。
これらの方法を組み合わせて使うことで、より効果的に床からの冷え込みを防ぎ、快適な空間を実現することができます。それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、ご自身の状況や予算に合った最適な方法を選びましょう。例えば、予算を抑えたい場合は断熱マットから始めて、効果が不十分であればホットカーペットを追加するといった段階的なアプローチも有効です。
壁の防寒対策:熱を逃がさない工夫

窓や床だけでなく、壁からも多くの熱が逃げていきます。断熱材がない家は特に、壁からの熱損失が室温低下に大きく影響します。そこで、壁からの熱を逃がさないための効果的な対策をいくつかご紹介します。
断熱シートの活用:手軽にできる壁の防寒対策
手軽にできる壁の防寒対策として、断熱シートの活用が挙げられます。アルミ蒸着シートや発泡ポリエチレンシートなど、様々な種類の断熱シートが市販されています。これらのシートは、壁と空気の間に空気層を作り、熱伝導を抑制する効果があります。特に、外壁に面した壁に貼ることで、効果を実感しやすいでしょう。取り付けも比較的簡単で、DIYでも手軽に取り組めます。ただし、シートの材質や厚さによって断熱効果は異なるため、商品選びには注意が必要です。 効果を高めるために、シートと壁の間に空気層を確保することが重要です。そのため、隙間なく貼り付けることがポイントです。
壁掛け暖房器具の設置:ピンポイントで暖める効果的な方法
壁掛け式の暖房器具は、直接壁に設置することで、効率的に部屋を暖めることができます。エアコンに比べて、局所的に暖めることができるため、電気代を抑えつつ、暖かさを感じやすいというメリットがあります。 ただし、設置場所によっては火災の危険性も伴うため、安全に配慮した設置が必要です。取扱説明書をよく読んで、安全な使用方法を理解した上で使用しましょう。また、機種によって消費電力や暖房能力が異なるため、部屋の広さや必要な暖かさなどを考慮して適切な機種を選びましょう。
家具の配置による工夫:賢い配置で寒さを軽減
家具の配置を変えるだけでも、壁からの冷気を軽減する効果があります。例えば、外壁に面した壁の前に、ソファや本棚などの家具を配置することで、壁からの冷気を遮断することができます。 また、家具の素材にも注目しましょう。木製の家具は、冷たい壁の冷気を和らげる効果があります。 さらに、カーテンを閉めて壁とカーテンの間に空気の層を作ることで、保温効果を高めることができます。 これらの工夫を組み合わせることで、より効果的な防寒対策が期待できます。
これらの対策を組み合わせることで、壁からの熱損失を最小限に抑え、より快適な室内環境を実現できます。それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、ご自身の状況に最適な方法を選択してください。
暖房器具の賢い活用術:光熱費を抑えつつ快適に

断熱材のない家では、暖房効率が低く、光熱費がかさんでしまうのが心配ですよね。しかし、適切な暖房器具を選び、賢く使えば、費用を抑えつつ、快適な室温を保つことが可能です。ここでは、光熱費を抑えながら、暖かく過ごすための具体的な方法を解説します。
適切な暖房器具の選び方
まず、家の広さや間取り、家族構成などを考慮して、最適な暖房器具を選びましょう。一口に暖房器具と言っても、様々な種類があります。それぞれの特徴を理解し、自分のニーズに合ったものを選ぶことが大切です。
- 石油ファンヒーター:暖まりが早く、広い部屋でも効果を発揮しますが、燃料の補充が必要で、換気にも注意が必要です。ランニングコストは比較的安価です。
- ガスファンヒーター:石油ファンヒーターと同様に暖まりが早く、広い部屋にも適しています。燃料の補充は不要ですが、ガス代はかかります。
- 電気ストーブ:コンパクトで手軽に使えますが、暖まるまでに時間がかかり、暖房範囲も限られています。電気代はかかりますが、手軽さが魅力です。
- エアコン:部屋全体を効率的に暖めることができます。初期費用はかかりますが、ランニングコストは比較的抑えられます。近年は省エネモデルも充実しています。
- パネルヒーター:輻射熱で部屋全体を暖めます。電気代はかかりますが、じんわりとした暖かさで、乾燥しにくいのが特徴です。
それぞれの暖房器具にはメリット・デメリットがあるので、比較検討し、ご自身のライフスタイルや予算に合ったものを選びましょう。特に、断熱性の低い家では、部屋全体を暖めるエアコンが効率的です。
タイマーや温度設定による節約
暖房器具を効果的に活用し、光熱費を節約するための具体的な方法として、タイマー機能や温度設定機能を積極的に活用しましょう。無駄な暖房を避けることで、エネルギー消費を大幅に削減できます。
- タイマー設定:外出時や就寝時は、タイマーを使って暖房を自動的に停止させましょう。帰宅時間に合わせて暖房をオンにすれば、無駄な電力消費を防げます。
- 温度設定:室温を1℃下げるだけで、光熱費を約10%削減できると言われています。快適な温度を保ちつつ、少しだけ温度設定を下げる工夫をしてみましょう。体感温度を上げる工夫として、暖かい服装をすることも効果的です。
- 節電モード:多くの暖房器具には節電モードが搭載されています。この機能を活用することで、消費電力を抑えつつ、快適な室温を保つことができます。
これらの機能を適切に活用することで、光熱費の節約に大きく貢献します。設定温度を調整したり、タイマーを活用するだけで、効果を実感できるはずです。
暖房効率を高める工夫
暖房器具の効率を高める工夫も重要です。ちょっとした工夫で、暖房効果をアップさせることができます。
- 窓の断熱対策:カーテンやブラインドで窓からの冷気を遮断しましょう。断熱効果の高いカーテンやブラインドを選ぶと、さらに効果的です。
- 隙間風の防止:窓やドアの隙間から冷気が入ってこないように、隙間テープなどを活用して、気密性を高めましょう。
- 家具の配置:暖房器具の前に家具を置かないようにしましょう。暖気が遮られてしまうと、暖房効率が低下します。
- こまめな換気:こまめな換気は、室内の空気を入れ替えることで、暖房効率を上げる効果があります。ただし、換気によって室温が下がるため、短時間で行うことが重要です。
これらの工夫は、特別な費用をかけることなく、簡単に実践できます。一つずつ試してみて、効果を実感してみてください。
適切な暖房器具選び、タイマーや温度設定の活用、そして暖房効率を高める工夫を組み合わせることで、断熱材のない家でも快適で経済的な冬を過ごすことが可能になります。ぜひ、これらの方法を試して、暖かく、そして節約できる冬を過ごしましょう。
DIYとリフォーム:費用と効果を比較検討

断熱材がない家の防寒対策において、DIYとリフォームはどちらも有効な手段です。しかし、それぞれに費用や効果、そしてかかる手間などに違いがあります。最適な方法を選ぶためには、それぞれのメリット・デメリットを理解し、費用対効果を比較検討することが重要です。ここでは、DIYとリフォームそれぞれの特性を詳しく見ていきましょう。
DIYによる防寒対策のメリット・デメリット
DIYは、自分のペースで作業を進められることや、費用を抑えられることが大きなメリットです。手軽にできる隙間風対策や、断熱シートの貼り付けなどは、DIYで十分対応可能です。しかし、複雑な工事や専門的な知識・技術を要する作業は、DIYでは難しい場合もあります。また、作業に失敗すると、かえって費用がかさんだり、家の状態が悪化してしまうリスクも考慮しなければなりません。
- メリット: 費用を抑えられる、自分のペースで作業できる、手軽にできる対策が多い
- デメリット: 専門的な知識・技術が必要な場合がある、作業に失敗するリスクがある、仕上がりが不十分になる可能性がある
リフォームによる防寒対策のメリット・デメリット
リフォームは、専門業者に依頼するため、確実な仕上がりと高い効果が期待できます。特に、内窓の設置や断熱材の追加など、大規模な工事が必要な場合は、リフォームがおすすめです。ただし、DIYに比べて費用が高額になることがデメリットです。また、工事期間が必要となるため、生活に支障が出る可能性もあります。業者選びも慎重に行う必要があります。
- メリット: 確実な仕上がり、高い効果が期待できる、専門業者による対応
- デメリット: 費用が高額になる、工事期間が必要、業者選びが重要
費用対効果の比較
費用対効果を比較する場合、対策の内容と家の状態を考慮することが重要です。例えば、隙間風対策であれば、DIYで手軽にできる隙間テープやパッキンの利用が費用対効果が高いでしょう。一方、内窓の設置や断熱材の追加など、大規模な工事が必要な場合は、リフォームによる効果の方が大きいため、費用が高額でも費用対効果は高いと判断できる場合があります。 それぞれの対策にかかる費用と、得られる効果を丁寧に比較検討し、長期的な視点も考慮に入れて判断することが大切です。 単純に価格だけで判断せず、数年後の光熱費削減効果なども含めて総合的に評価しましょう。
最終的には、ご自身の予算、DIYスキル、家の状態、そして求める快適さのレベルなどを総合的に考慮して、DIYとリフォームのどちらを選ぶか決定することをお勧めします。
根本的に寒い家を温かくする方法はリフォーム

断熱テープや暖房の見直しで部屋の寒さが改善しない場合は、リフォームを検討してみましょう。リフォームは老朽化した家を直すイメージがありますが、断熱性を上げるリフォームもあります。近年は、二酸化炭素削減の観点から国や自治体も断熱リフォームを推奨しており、補助金なども豊富です。ここでは、家を断熱するメリットや方法について紹介します。
家を断熱リフォームする魅力
家を断熱リフォームすれば、生活のしやすさが格段に向上します。家が寒いと動く気力がなくなり、気分も落ち込むといった方も珍しくありません。断熱効果を高めて家の中で生活しやすくなれば、寒い冬も快適に過ごせるでしょう。
家の断熱リフォームは、内壁や外壁の中に断熱材を入れる大規模なリフォームのほか、断熱性能の高い窓やドアをつける部分的なリフォームがあります。どちらも、家に住みながらリフォームが可能なので、一時的な引越しをする手間もありません。特に、築年数が経って断熱材が入っていない家は効果が実感しやすいはずです。
断熱すれば光熱費も節約できる
断熱性の低い家は、光熱費もかかりがちです。温度を高く設定しても部屋が暖まらず、ガス代や電気代がかさむばかりといったケースも珍しくありません。断熱リフォームをすると光熱費が格段に下がることもあるでしょう。
断熱リフォームは、一定の費用がかかります。しかし、光熱費が毎月節約できれば数年たてばリフォーム費用を相殺できる可能性もあります。特に、寒冷地に住んでいて家が寒い場合は、効果が実感できるでしょう。断熱リフォームする際に、床暖房など家に合った暖房を設置する工事も行えます。
補助金も活用できる
前述したように、国や自治体も断熱リフォームに力を入れており、子育て世代や若夫婦といった特定の年齢がリフォームを行ったり、断熱窓設置など特定の工事をしたりした際に補助金を支給しています。10万~100万円程度の補助が受けられれば、経済的な負担を軽くできます。
また、国の補助金と併せて自治体の補助金を利用できれば、さらにお得にリフォームができます。自治体が独自に実施している補助金は、地域のニーズに合わせたものも多いので、まずは確認してみましょう。
寒い家を根本的に温かくするには断熱リフォームも視野に入れよう

断熱材のない家でも、適切な対策を施せば、暖かく快適な冬を過ごすことは可能です。 この記事では、窓・ドア、床、壁からの冷気対策から、暖房の賢い活用術、そしてDIYとリフォームの比較まで、多角的な視点から防寒対策を解説しました。
重要なのは、家の構造や自身の予算、そして快適さのレベルを考慮し、最適な対策を選ぶことです。 隙間風を防ぐための気密性向上は、どの対策にも共通して効果的な第一歩です。 窓には断熱カーテンや内窓、床には断熱マットやカーペット、壁には断熱シートなどを活用することで、手軽に効果を実感できるでしょう。 さらに、暖房器具を適切に使いこなし、タイマーや温度設定を工夫することで、光熱費の節約にも繋がります。
DIYで手軽にできる対策から、リフォームによる本格的な断熱強化まで、選択肢は様々です。 費用対効果を比較検討し、優先順位を付けて対策を進めていくことが大切です。 例えば、まずは費用を抑えやすい隙間風対策から始め、効果を見てからより本格的なリフォームを検討するのも良いでしょう。当社でも、断熱リフォームの相談を行っています。小さいことでもお気軽にご相談ください。
寒さ対策は、単に温度を上げるだけでなく、体の芯から温まる工夫も重要です。 暖かい服装や、こまめな水分補給なども忘れずに行いましょう。 快適な室温を保つことは、健康な冬を過ごすためにも不可欠です。
この記事が、断熱材のない家で快適な冬を過ごすためのヒントになれば幸いです。 寒さを乗り越え、暖かく、そして心豊かな冬をお過ごしください。
Q.断熱リフォームはどのくらいの工期で行えますか? A. 工事によって異なりますが、窓を交換する程度のリフォームなら1日で行えます。
Q. 断熱リフォームは住みながら行えますか? A.家中の部屋の内壁を一度に壊して断熱リフォームをするといったケースでない限り、住みながら行えます。